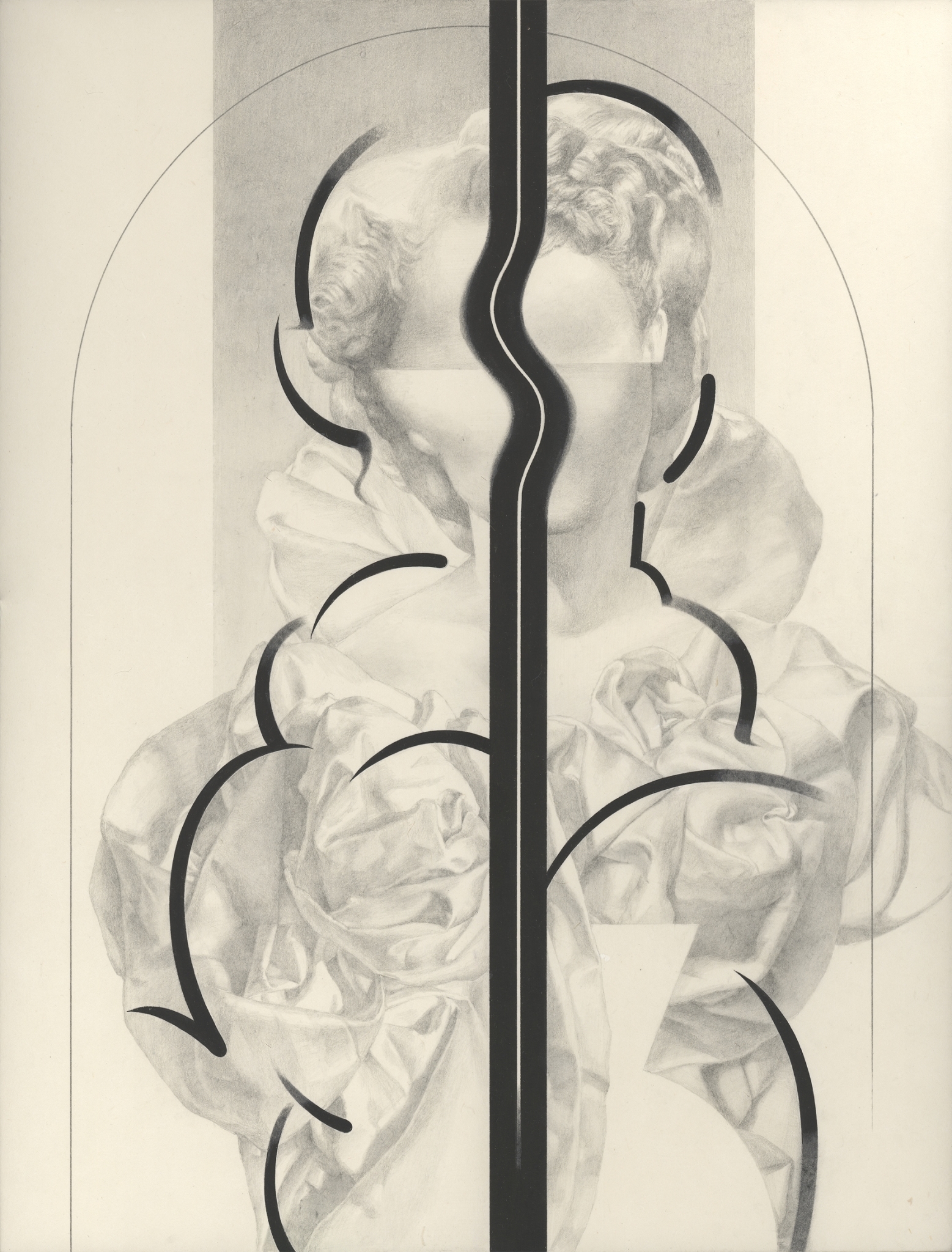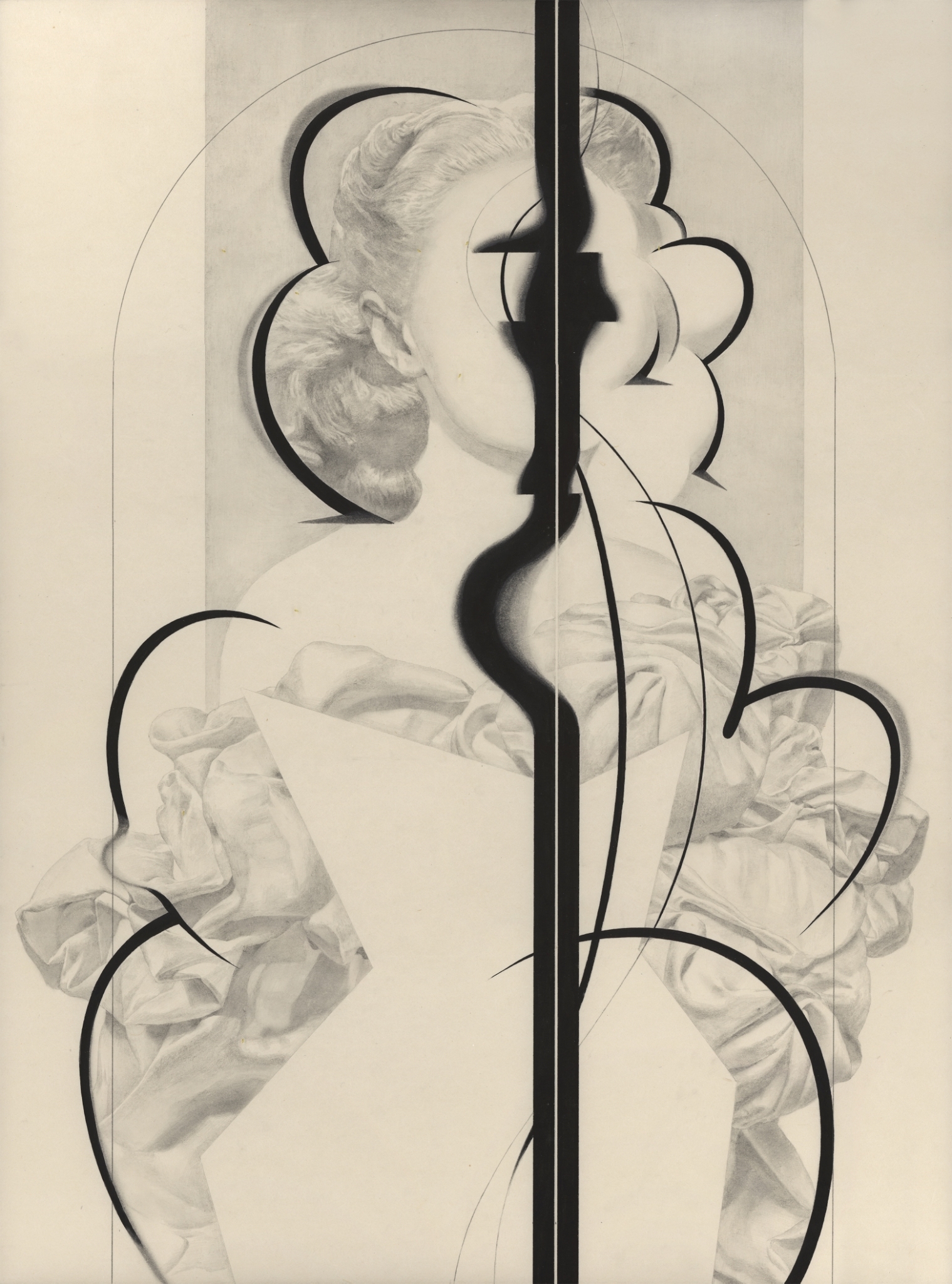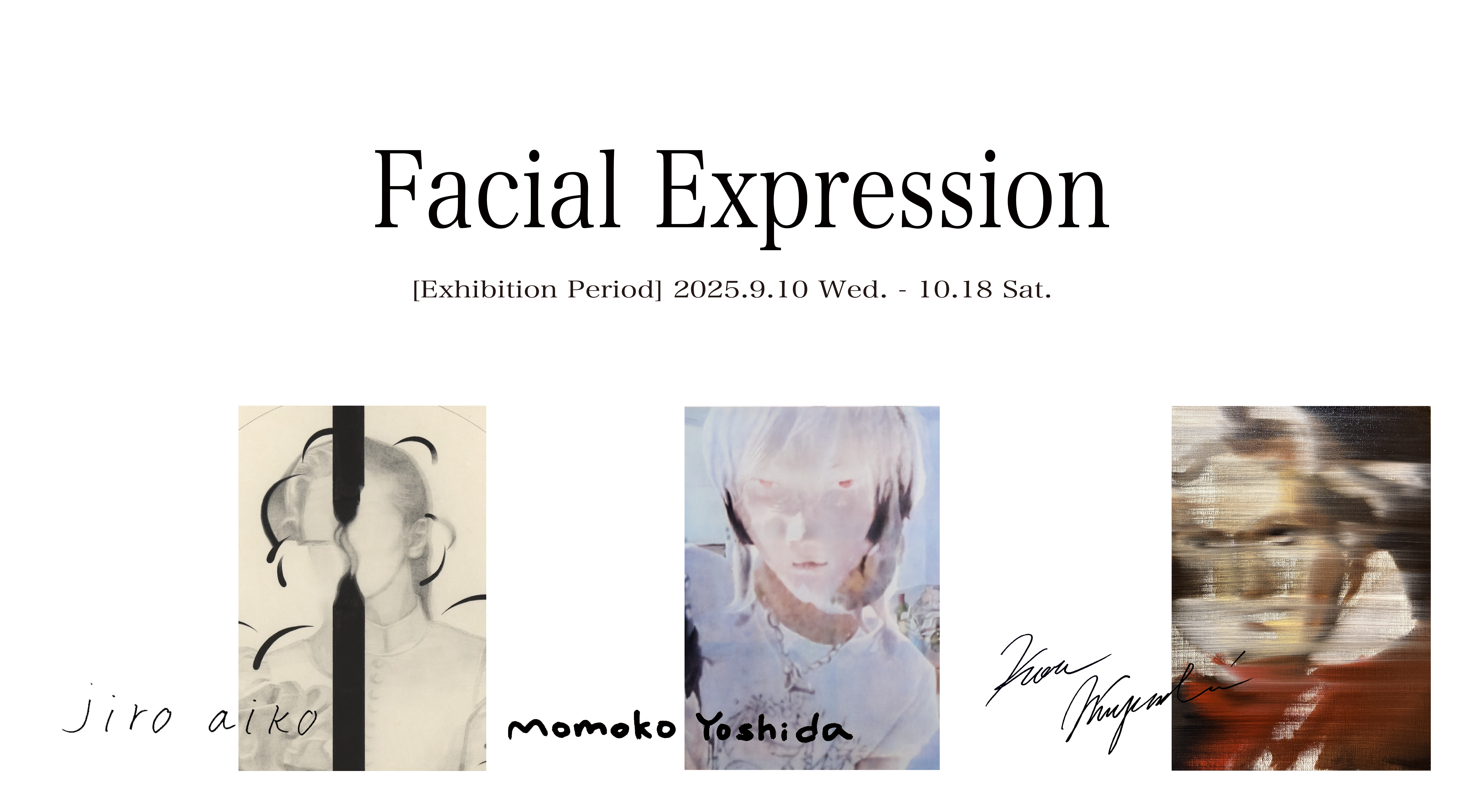ARTIST

愛甲 次郎
東京藝術⼤学⽇本画専攻を卒業後、東京を中⼼に画家として活動。
⿇紙に鉛筆や墨など繊細な素材を⽤いて、⼈の内⾯に潜む脆さや傷つきやすさを描き出す。
ぼんやりと浮かび上がる肖像の輪郭に寄り添う墨は、消えゆく存在の記憶を留め、表情の中⼼を⾛る線は⼈物の曖昧さを印象づけます。
主な個展に「誰かが⾃分のために祈ってくれるということ」(CLEAR GALLERY TOKYO、東京、2024年)、「ピアニシモな鎧」(TAKU SOMETANI GALLERY、東京、2023年)、「fragments」(銀座蔦屋書店、東京、2022年)
Artist Statement
私の制作は「繊細であること」「脆く、傷つきやすいこと」「揺れやすく、移ろいやすいこと」これらを肯定する姿勢から始まっています。鉛筆で描かれるモチーフは輪郭が曖昧であったり、ブレていたり、乱視的で焦点の定まらない表現をとることが多くあります。それは、「繊細さ」や「移ろいやすさ」を表現しながらも、対象を一方的に把握したり、確定したかたちに閉じ込めることに対する私なりの距離の取り方でもあります。見ることは常に揺らいでいて、不安定で、不完全なものであり、定着力の強くない鉛筆の表現はおぼつかない記憶のような存在として描こうとしています。
自分の中の繊細さや傷つきやすさを抑えて、はっきりとした意見を持ち、迷いなく前に進もうとしたとき、どこかで違和感を覚えることがありました。そのとき私が手に取っていたのは、きっと“金属の鎧”のようなもので、身を守るかわりに、他者の繊細さに触れにくくなっていたのだと思います。自分の脆さに蓋をしてしまえば、他者の体温にも気づきにくくなり、ときに無自覚な攻撃性を帯びてしまうこともある。だからこそ私は、自身の壊れやすさに驚くことはあっても出来る限り金属の鎧を手放していきたいと考えます。
黒い墨の線には、複数の役割が込められています。
それはモチーフを固定する接着剤のような存在であり、同時に、拘束具や鎧のような硬さや緊張感を伴っています。線はモチーフの輪郭に忠実に沿うのではなく、かたちを完全に定めずに支えるような働きをしています。そこには強さをまといたいという憧れと、そうすることで繊細さを損なうことへの戸惑いが交錯しています。線は守るために引かれたようでありながら、鎧をもつことの違和感を表し、その両義的な作用によって画面の中に微細な揺れと緊張を生み出そうとしています。
BIOGRAPHY
- 東京都生まれ
- 2016
- 東京藝術大学 美術学部絵画科日本画専攻 卒業
CV
- 2024
- Idemitsu Art Award 2024 入選
EXHIBITIONS
- 2018
- 【グループ展】「それぞれのパーティ/かまわぬ」小林直博、愛甲次郎合同展 GALLERY X BY PARCO SHIBUYA(東京)
- 2019
- 【個展】「覚束なさへ」CANDLE CAFE & Laboratory △ll(東京)
- 2022
- 【個展】「湯煎するように」CANDLE CAFE & Laboratory △ll(東京)
【個展】「fragments」銀座 蔦屋書店(東京) - 2023
- 【個展】「だいじょうぶ。」 MAT(東京)
【個展】「ピアニシモな鎧」 TAKU SOMETANI GALLERY(東京)
【グループ展】「UNLOGICAL 06」MONO.LOGUES(東京)
【グループ展】「Idemitsu Art Award 2024」国立新美術館(東京) - 2024
- 【個展】「誰かが自分のために祈ってくれるということ」CLEAR GALLERY TOKYO(東京)
- 2025
- 【グループ展】「an brace」愛甲次郎/柿坪満実子 CANDLE CAFE & Laboratory △ll(東京)
【グループ展】「em brace」愛甲次郎/柿坪満実子 TAKU SOMETANI GALLERY(東京)
ARTWORK PROVIDED
- 2017
- サンプラー・アーティストblahmuzik
- 2018
- JET SET開業20周年企画
- 2018
- りんご音楽祭 ポスター
- 2024
- iri「Faster than me」
WORKS